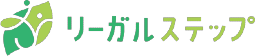相続に関するFAQ
不動産売却
- 遺産の中に不動産があるので、売却して代金を相続人で分けたいのですが、どうすればよいでしょうか?
-
ご依頼いただければ、相続登記の後に『売却代理』や『売買代金の分配』も含めて、遺産整理業務として受任することが可能です。遠方の不動産であってもご対応させていただきます。
- 相続した建物を売却しようとしたら未登記でした。どうしたらよいのでしょうか?
-
売却の前提として建物表題登記(建物の登記簿謄本を作成する登記)をしなければいけません。なお、この登記手続きは『土地家屋調査士』がする必要があります。なお、その後の所有権保存登記は『司法書士』がする必要があります。当事務所代表は両方の資格がございますので一括してお引受け可能です。
- 相続した土地を売却しようとしたら相続登記手続きだけではなく、確定測量までしてほしいと言われたのですが必要なのでしょうか?
-
土地売却を行う際の測量は義務ではありません。売主と買主の双方が合意すれば、登記簿上の面積で売買契約が可能です。ただし、測量していない又は昔に測量された土地の場合、現在よりも測量精度が落ちるため登記簿上の面積と異なることが多々あります。結果的に、そのことで隣接している所有者とトラブルになったり、売却査定額に影響を及ぼすことがあるので確定測量した方が良いでしょう。
遺産分割
- 相続人の内に認知症患者がいるのですが、遺産分割はどのように進めればよいでしょうか?
-
認知症が比較的軽度で、意思能力に問題が無い場合であれば、成年後見制度を利用せず遺産分割協議をすればよいでしょう。これに対して、認知症がある程度進行しており、意思能力に問題がある場合、家庭裁判所に対して『成年後見人の選任申立て』を行い、選任された成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。意思能力の有無の判断に迷う場合は、医師の診断を受けることも選択肢のひとつに入れると良いでしょう。
- 相続人の内に未成年者がいるのですが、遺産分割協議はどのように進めればよいでしょうか?
-
親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行うのが原則ですが、親権者も相続人に該当する場合は未成年者と利益相反関係になるため、家庭裁判所に対して『特別代理人の選任申立て』を行い、選任された特別代理人と遺産分割協議を行うことになります。
- 遺言の内容と異なる遺産分割協議はできますか?
-
相続人全員(受贈者がいれば、その者も含む)が合意すれば、遺言と異なる内容の遺産分割も可能です。但し、遺言で遺産分割が禁止(最大5年)されている場合は期間経過後でなければできません。
- 遺産の一部だけを遺産分割することはできますか?
-
できます。ただし、残りの財産の分割に影響がでるか否かも考慮したうえで慎重に検討する必要があります。
- 父が亡くなり、遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。この場合どうなりますか?
-
認知された子を見落として行われた遺産分割協議は無効です。その方を含めた相続人全員でやり直す必要があります。但し、『死後認知』だった場合は遺産分割協議は有効のままです。その場合、認知された子の相続分を金銭で支払う必要があります。
- 相続人の一人が海外に居住している場合でも、遺産分割協議はできますか?
-
遺産分割協議をすることが可能です。遺産分割協議書を各相続人の持ち回りで作成することも可能ですし、遺産分割証明書として海外居住の相続人の分を別途作成して進めることも可能です。但し、印鑑証明書の代わりに日本の在外公館の領事や外国の公証人の面前で、本人が遺産分割協議書に署名し、本人の署名であることの『署名証明を取得』することが必要です。
- 相続人のひとりが行方不明で連絡がつかない場合、遺産分割協議はできないのですか?
-
家庭裁判所に『不在者財産管理人選任申立て』をし、その選任された不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになります。その他、不在者が7年以上生死不明の場合や、事故や遭難などで1年間生死不明な場合に、行方不明者を死亡したとみなす、「失踪宣告」という制度もあります。
- 遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合はどうなりますか?
-
基本的には既にした遺産分割協議は有効です。新たに見つかった遺産についてのみ再度相続人間で遺産分割協議をすれば問題ありません。また、遺産分割協議を、相続人全員の合意によってやり直すことも最高裁の判例上認められています。
- 父の遺産に賃貸不動産が含まれています。遺産分割協議が成立するまでの賃料はどうなりますか?
-
法定相続人が法定相続分に従って取得します。なお、遺産分割後の賃料債権は、その不動産を取得した相続人が取得することになります。
遺言
- 父は、認知症の母のお世話をすることを前提に、長男に全ての財産を遺贈したにもかかわらず、長男が母のお世話をしない場合どうすればいいの?
-
他の相続人は、長男に相当の期間を定めて、義務の履行を催告し、その期間内に履行されない場合は、家庭裁判所に遺贈の取消しの申立てをすることができます。遺言の取消が認められた場合には、母のお世話や遺産のことについて、改めて遺産分割協議で決めることになりますが、協議がまとまらない場合は遺産分割調停を申し立てることになります。
- 父は生前、公正証書遺言を作成していたようですが探す方法はありますか?
-
平成元年以降の公正証書遺言であれば最寄りの公証役場にて調査可能です。平成元年以前の公正証書遺言はコンピュータ化前のため、実際に公正証書遺言を作成した公証役場でなければ調べることはできません。なお、司法書士が代理して調査することも可能です。
- 遺留分を侵害する遺言は無効ですか?
-
相続人の遺留分を侵害する遺言であっても、その遺言は有効です。 但し、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求権を行使された場合、侵害額を金銭によって支払う必要があります。
- 遺言書は、『検認』という手続きが必要と聞いたのですが本当に必要でしょうか。
-
『公正証書』と『自筆証書遺言書保管制度』を用いたもの以外の遺言については、家庭裁判所において検認手続きが必要です。
- 遺言書が2通あるのですが、どちらが有効でしょうか?
-
2通の遺言書の内容が抵触する場合、作成日付を基準に『内容が抵触する範囲』で、 後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。
- 後見人が本人の代わりに遺言書を作成することはできますか?
-
できません。但し、被後見人の判断能力が一時的に回復した場合に、2人以上の医師が立ち会い判断能力を欠く状態になかったことを遺言書に付記すれば、被後見人が残した遺言は有効になります。
相続放棄
- 相続放棄と遺産分割協議で財産を一切もらわないことは同じでしょうか?
-
同じではありません。遺産分割協議で財産をもらわないことは、「相続財産権」を放棄したというだけですので、そもそも「相続人でなくなる」相続放棄とは異なるものです。ですので、もし借金があればマイナスの財産は引き継いだままです。仮に遺産分割協議書に借金を引き継がない旨が書かれていても、そのことを債権者に主張できません。
- 相続の熟慮期間とは何ですか?いつからいつまでのことですか?
-
相続人は、原則、自己のために相続の開始があったことを『知った時から3ヶ月以内』に、相続について単純もしくは限定の承認、または放棄しなければならず、この期間のことを熟慮期間といいます。原則、この期間を過ぎれば自動的に単純承認したものとみなされます。
- 父が亡くなったことを知り1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があることがわかりました。この場合は、相続放棄はできないのですか?
-
被相続人の相続財産(この場合は債務)を知らないことにつき、相続人に正当な理由がある場合であれば、相続放棄ができる可能性があります。判断に迷う場合は一度ご相談ください。
- 相続財産の内から葬儀費用を支出した後に、相続放棄をすることはできますか?
-
葬儀費用の支出については、不相当に高額なものでなければ、法定単純承認事由としての相続財産の「処分」にはあたらず、その後に相続放棄をすることができます。
- 相続放棄をしても、生命保険金は受け取れますか?
-
生命保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有の財産となるので、相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができます。ただし、税務上、相続放棄により相続人ではなくなるため、「法定相続人×500万円」まで課税されない非課税規定が適用されないので注意を要します。
その他相続
- 亡き父の預金を相続人のひとりが勝手にキャッシュカードで引き出していた場合どうすればよいでしょうか?
-
不法行為による損害賠償請求か不当利得による返還請求をすることが考えられます。ただ、いきなり争いにもっていくのではなく、預金を何のために使ったのか話し合いの場を設けて、話し合いで解決可能か模索するのも良いかもしれません。
- 借地権付きの建物を相続した場合、何か特別な手続きは必要ですか?
-
借地権付きの建物を相続登記すれば他に手続きは不要です。ただし、借地人が変わった旨を地主に連絡をしたほうが後々のトラブルを防ぐためにも良いでしょう。
- 相続人が1人もいないのですが、この場合の私の相続財産はどうなりますか?
-
相続財産管理人の選任、相続人の捜索、相続財産の清算という順番を経たうえでも相続人が存在しない場合は、特別縁故者の有無が問題となり、特別縁故者もいない場合は、最終的に相続財産は国庫に帰属します。
- 遺留分侵害額請求権の行使は、どうすればいいですか?
-
遺留分侵害額請求権の行使は、裁判上でする必要はなく、相手方に意思表示すれば効果が生じます。 ただし、言った言わないの水掛け論にならないように配達証明付内容証明郵便によることをおすすめします。
後見に関するFAQ
- 父が認知症です。父所有の不動産を売却したいのですがどうすればよいでしょうか?
-
成年後見人選任申立てをする必要があります。
ただし、注意点として以下のことがあります。
1.成年後見人が不動産売却を本人のためにならないとして売却が認められない場合
成年後見人はあくまで『本人のため』の代理人です。不動産の売却が本人のためとならないと判断されてしまえば、売却できないことになります。
2.成年後見は不動産売却後も原則被後見人が亡くなるまで続く制度であること
不動産売却のために成年後見制度を利用したとしても原則本人が亡くなるまで続く制度ですので任意に辞めさせることはできません。
信託に関するFAQ
- 信託って色々あるけれども家族信託とはなにか?
-
「民事信託」の中でもとりわけ、家族や親族を受託者として財産管理を任せる仕組みを 「家族信託」といいます。これとは別に信託銀行や信託会社が報酬を得るための業務として行うものを「商事信託」といい代表的なものに投資信託があります。
不動産登記に関するFAQ
- 一筆の土地の一部分だけを売ることはできますか?
-
一筆の土地の一部分であっても、それがどの部分か特定できるのであれば、売買することは可能です。ただし、登記簿上一部分についての所有権移転登記はできません。そこで、この場合は事前に分筆登記を行ったうえで、所有権移転登記をすることになります。
- 自宅の購入にあたり、夫婦の共有名義にしたいのですが、持分はどう決めればいいでしょうか?
-
売買代金の出資割合に応じて定めるのが原則です。 もし、これと異なる割合で定めると、実際の出資割合より少ない持分を得た者から、実際の出資割合より多い持分を得た者に対し、贈与されたとみなされて、贈与税が課税されることがあります。
- 権利証を無くしたのですが再発行できますか?
-
できません。 もし、売却等の権利証が必要な場合は司法書士が『本人確認情報』という権利証に代わる書類を作成することにより手続き可能です。
- 住宅ローンを完済したら、抵当権抹消の案内などの書類を受取りましたが、どうすればいいのですか?
-
支払い続けた住宅ローンを完済すると、金融機関から完済証明などの書類と併せて、抵当権の抹消に必要となる書類が交付されます。 住宅ローンの完済で抵当権は消滅していますが、抵当権の登記は自動的に抹消されないため、抵当権抹消の登記申請が必要です。